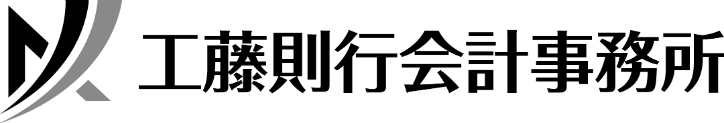日経新聞の広告で目に留まった、
直木賞作家の中島京子さんの「長いお別れ」(文庫本版)を読みました。
【あらすじ】
帰り道は忘れても、難読漢字はすらすらわかる。
妻の名前を言えなくても、顔を見れば、安心しきった顔をする――。
東家の大黒柱、東昇平はかつて区立中学の校長や公立図書館の館長をつとめたが、
十年ほど前から認知症を患っている。長年連れ添った妻・曜子とふたり暮らし、娘が三人。孫もいる。
“少しずつ記憶をなくして、ゆっくりゆっくり遠ざかって行く”といわれる認知症。
ある言葉が予想もつかない別の言葉と入れ替わってしまう、迷子になって遊園地へまよいこむ、
入れ歯の頻繁な紛失と出現、記憶の混濁–日々起きる不測の事態に右往左往するひとつの家族の姿を通じて、
終末のひとつの幸福が描き出される。著者独特のやわらかなユーモアが光る傑作連作集。
著者の中島さんは実際に認知症介護を経験されていたそうで、とてもリアリティがありました。
ユーモラスな書き口なので、凄惨さなどはあまり感じませんでしたが、
実際には、体力的、精神的にも非常に厳しいものなのではないか、と感じました。
内閣府によると、65歳以上の高齢者の認知症患者数と有病率の将来推計についてみると、
平成24(2012)年は認知症患者数が462万人と、65歳以上の高齢者の7人に1人(有病率15.0%)であったのが、
平成37(2025)年には約700万人、5人に1人になると見込まれているそうです。
将来的に自分が介護経験することにならないとは言えませんし、他人事ではないですね。
ちなみに、この本の中で、「施設に入るのに家を売る?」、ということを考えるくだりがあるのですが、
もしも家の名義が、認知症を患っている本人ならば、簡単に売ることはできないのでは?
もしかして奥さんの名義なのだろうか?
と、変なところが気になってしまいました。
認知症になってしまうと、契約に関する正常な判断ができない、
ということで本人は自宅の売却契約をすることができなくなってしまいます。
それでは、配偶者や子供が本人の代わりにできるのかというと、そう単純にはいきません(続く)